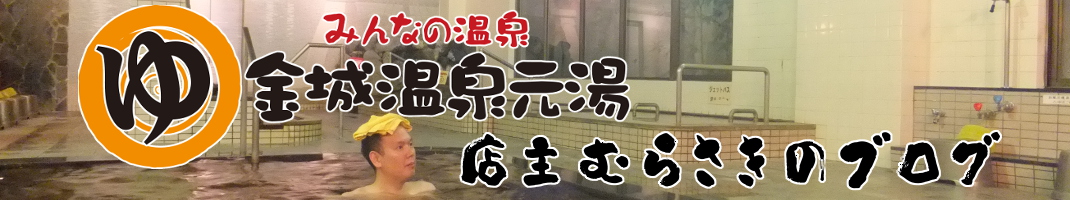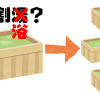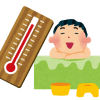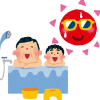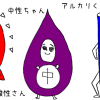新しいくて大きいのがスーパー銭湯で古くて小さいのが銭湯?
半分正解!?
確かに改装された新しい銭湯はありますが、規模の大きな銭湯はあまり見かけませんね。
また新たに作られるお風呂屋さんは、ほとんどスーパー銭湯です。
実は「銭湯」と「スーパー銭湯」は、法令により明確に分類されています。
条例による分類
「公衆浴場法」という法律で、入浴施設を「公衆浴場」と名付けています。
※ [公衆浴場法 第一条]

公衆浴場は法律で定めている
この「公衆浴場」を、各都道府県が制定する条例により以下の2つに分類しています。
- 普通公衆浴場(いわゆる銭湯)
- その他の公衆浴場(銭湯以外。スーパー銭湯・健康ランド・家族風呂など)
※ [石川県公衆浴場基準条例 第二条]

銭湯は条例で定めている
なぜか公衆浴場法ではなく条例で分類しているのですね。
そのため、普通公衆浴場ではなく「一般公衆浴場」、その他の公衆浴場ではなく「特殊公衆浴場」と呼ぶところもあるようです。
銭湯であるためには
では銭湯(普通公衆浴場)として分類されるための条件は何なのでしょうか。
- 設置制限
「銭湯と他の銭湯の間が、350メートル以上離れている」
※ [石川県公衆浴場基準条例 第三条] - 衛生基準
「脱衣場と浴室の”広さ”が基準以上」
「浴槽の”深さ”と”広さ”が基準以上」
「浴槽に階段や手すりを設ける事」
※ [石川県公衆浴場基準条例 第四条] - 価格統制
「”物価統制令”に定められた入浴料金」
※ [公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律 第二条]
もっとも分かり易いものは「入浴料金の違い」のようです。
「銭湯」には価格統制により「入浴料金の上限」が決められているのです。
なぜ銭湯とスーパー銭湯は区別されるの?
なぜ「入浴料金」で銭湯を区別する必要があるのでしょうか?
条例にはこのように書かれています。
“普通公衆浴場(銭湯)は、利用目的及び利用形態が地域住民の日常生活にとつて保健衛生上必要な施設として利用される公衆浴場”
※ [石川県公衆浴場基準条例 第二条]
つまり、各家庭にお風呂が普及していなかった時代に、地域の方に日常的に「安価で利用」していただくために「価格統制(入浴料金を低く抑える)」を行う必要があったようです。
もう安い風呂屋さんはいらない?
では、各家庭にお風呂が普及した今となっては「銭湯」は不要なのでしょうか?
ありがたい事に、今でも銭湯には家にお風呂があるのにもかかわらず来ていただけるお客さまがいらっしゃいます。
「大きなお風呂が好き」「お風呂友だちがいるから」「家の風呂掃除が面倒やし」「独り身でお風呂溜めるのがもったいない」など理由はいろいろ。
広くて立派な温泉旅館やスーパー銭湯のお風呂で「自分へのご褒美」にはならなくても、低価格で提供できる銭湯だからこそ、今でも生活の一部になることができているのだと思います。
これからも銭湯!
低い入浴料金が、設備投資などの足かせになることもあります。
しかし「気軽に利用しやすい料金」にしばられているからこそできる役割が銭湯にはあると思います。
皆さんに気軽に入ってもらうための分類である”銭湯”は、私たち”銭湯を営む人”の進むべき道しるべになっている気がします。

帰られるお客さんの笑顔が私たちのいちばんの幸せです